カツ…カツ…
幻想空間の、先の見えない廊下を歩いている。
反響しているのは自分の足音だ。俺はこの音がとても苦手だった。
たった1つのこの音は、より凛とした静寂を突きつけてくる。
何故だろう。硬質な己の足音は幼い日、父にそばに居てくれとせがんだ記憶を想起させる。
あの時に響いた足音は、父のモノだったはずなのに。
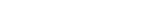
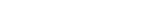 Good night
Good night
「何やってんだお前…」
扉を開ければそこにはベアトがいて、ベアトは当然のようにこの静寂を打ち破ってくれるという希望があった。
だが扉を開けた瞬間にベアトは唇に指を当て、「しー」というポーズをこちらに向けてきた。そしてそのまま固まってしまった。
その膝には、幼い自分自身が頭を預け、寝息を立てていた。
「戦人………え?戦人っ!? はぁ?じゃあこれは…?」
小声のまま狼狽えるベアトに疑問を投げつつ、向かいのソファーに腰掛ける。
「これって……お前の仕業じゃないのかよ…」
そのまま視線をベアトの膝の上、幼い自分に。
パッと見、5,6才と言ったところだろうか。特徴的な赤毛のみならず、その小さな頭が魔女のスカートに埋もれている。
何故だろうか、少年が身を預けている彼女の膝は柔らかいのだろうなぁ、などという少し間の抜けたことを考えた。
「知らん。というか妾はこれがお前だとばっかり…」
「俺はこっちだよ。そんなチビと間違うなんて、老眼なんじゃねーか?」
「それは……魔法、お師匠様の仕業かと。日頃いい子にしている妾への嬉しいビックリサプライズご褒美だろうなーやったー!ってな」
「お前がいい子なら全人類は天使かガンジーだ。そんでビックリとサプライズって微妙にかぶってねぇか?」
「どうでもよいわ」
心底どうでもよさそうに呟いたベアトは所在なさげに膝の上の幼子に視線を落とす。
先程より幾分か声のトーンをあげているが、少年が目覚める気配はない。
数秒か数十秒か、はたまた数分かの、そう長くはない沈黙。
破ったのは戦人だ。
「……で、何でお前がそれを膝枕でねんねさせてんだよ。あーあー、千年を生きた魔女様にロリコン趣味がおありとはなぁ」
「戦人!そういうのはショタと言うのだぞ!妾はちゃんと勉強した」
「どうでもいいな」
会話があらぬ方向へ向かいそうな気配がしたため、とりあえず打ち切る。
しかしどうにも、目の前の女の膝に幼い日の自分がいるという現状に居心地の悪さを覚えるわけで。
そんな状況を打破するために、数分の後に彼はまた口を開いた。
「で、何でお前の膝でそいつは寝てんだよ。ってか、そもそもそいつは何なんだよ」
お前、俺(小)に何しやがった?言外にそういったニュアンスを含めて問いかければ彼女の頬がぷぅと膨れた。
「知らんといってるだろぉ?ただコイツは言っていたぞ。『あんた、誰だ?俺は右代宮戦人だ』って」
ベアトがたどたどしい口調で少年のマネをする。
「だから、妾は師匠の魔法でお前が小さくなったのかと思った。時を戻す魔法において、師匠の腕はピカイチだからな」
「で、大ハズレだったわけだ」
「うむ。超ビックリしたんだぞ、あれ?戦人が二人?妾ってばいつの間に新たな黄金郷に至ったの?的な」
「気持ち悪ぃ黄金郷を新設してんじゃねーよ!そもそも、俺がこうしている以上、それは俺じゃねーってことだろうが」
ゾッとする意見に噛みつけば、彼女は少し悲しそうに目を伏せた。
長いまつげが瞳を覆う。その視線の先には自分ではなく、少年がいる。
「それは……違う」
ぽつり、漏れた声は小さいが、ハッキリと言い切った。
「それでも、妾はこやつが戦人、お前だと思った。」
彼女の視線があがり、真正面から見つめられる。
「………何で?」
またしても、沈黙に耐えきれずに声を発したのはこちらだ。
「……って……ったから」
躊躇っているのか、覇気のない彼女の声はうまく聞き取れなかった。
何て言ったんだ?促せば、意を決したように彼女がハッキリと告げる。
「『寂しいから、一緒にいてくれ』と。お前は…いや、こいつはそう言ったから」
真っ青な瞳が、真っ直ぐに自分を射貫いている。彼女の唇の赤がやたらと目に付く。
「だから、妾はこいつがお前だと思った。それだけだ」
そう言って彼女は口を噤んでしまった。
「……阿呆か」
そんな彼女に対して、自分が投げかけたのは否定の言葉。
「俺はそんなこと言わねーよ」
そう言って笑う。目の前の少年の仕業だろうか。耳鳴りのように廊下に反響する足音が聞こえる。
カツ、カツ、響く足音。父親の背中。一度だけ頭に置かれた大きな手のひら。
『行ってくる』……そんな言葉。
「……そんなことはないぞ」
柔らかい声色が、意識を戻した。
耳鳴りのような足音が引いていく。
「……よっし!わかった!」
「…はぁ?」
何をわかったと言うのだ。
そう問いかける前に彼女は空いた右膝をポンポンと叩き、胸を張ってみせる。
「さぁこい!大丈夫、左側には先客がいるが、右側ならばもれなく空席だ!」
「……何がわかったんだよ!誰が行くかバカ野郎!」
そう声を荒げると、少年が一度だけ反応した気がした。
ベアトが無言で声のトーンを落とすよう身振りをしたので、それには素直に従った。
「……なぁ」
数十秒後、口を開いたのは彼女の方。
「寂しいんだろ?こいよぉこいよぉーきちゃえばいいだろぉー?
「寂しくねぇよ」
「寂しくねぇはずねぇじゃん。こいつ、寂しかったって言ってたぞ」
「そりゃお前……そいつはガキだからだろうが。大体そりゃあ俺じゃねぇ」
「お前だよ。そんで、お前だってガキだよ」
そう言って、とても楽しそうに笑う。気にくわないその笑い顔。
「ガキが、図体だけ大っきくなっちまったんだろぉ?だからさ、来いって」
「千年の魔女様の前では誰だって赤ん坊も同然だろが……ああ、でも」
立ち上がり、向かいのソファーに向かい、腰掛ける。
彼女の左側。先客のその横に。
「……でも、こいつは寂しかったから。
だから、うん。そのまま、今晩はそいつの側にいてやってくれねぇか?」
そう言って笑った。
手持ちぶさたになった右手で撫でた少年の頬は暖かかった。
「……お前は寂しくないのか」
「おう。だからさ、ん?だから、ってのも変な話だが、頼むぜ。こいつの側にいてやってくれよ」
不満げな彼女にそう告げてやれば、不安げな目で問いかけられた。
「それは……お前の慰みになるのか?」
優しい目だった。
「ああ」
だから、
「それなら、ああ。承ったよ。この少年の安らぎは、千年の魔女、ベアトリーチェの名に賭けて保証しよう」
少し、甘えてみようと思った。気恥ずかしさからの茶化すような言葉は、お互い様だ。
「大げさなんだよ、お前は」
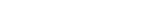
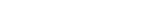 Good day Good night
Good day Good night
「大丈夫かって?大丈夫に決まってんだろうが」
右側には幼い日の自分、その先には千年の魔女。
「だって俺はもう一人で大丈夫だから。いや、違うな」
彼らはやわらかな寝息をたてている。自分の声だけがやたらと響く。
「一人じゃないからな。だから、平気だよ」
そう言って、腕を伸ばして金の髪を指で梳く。
彼女が笑った気がした。
やこ